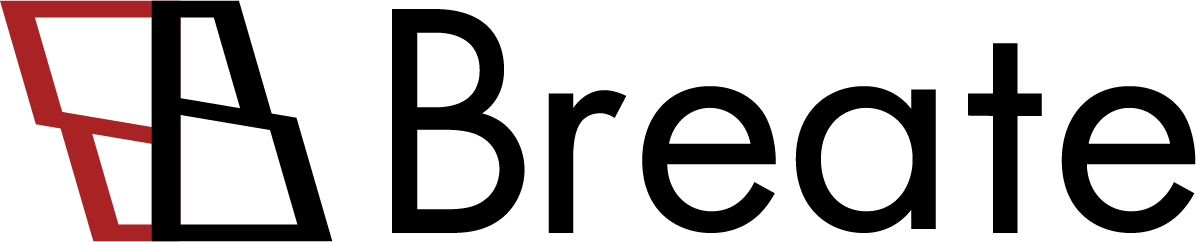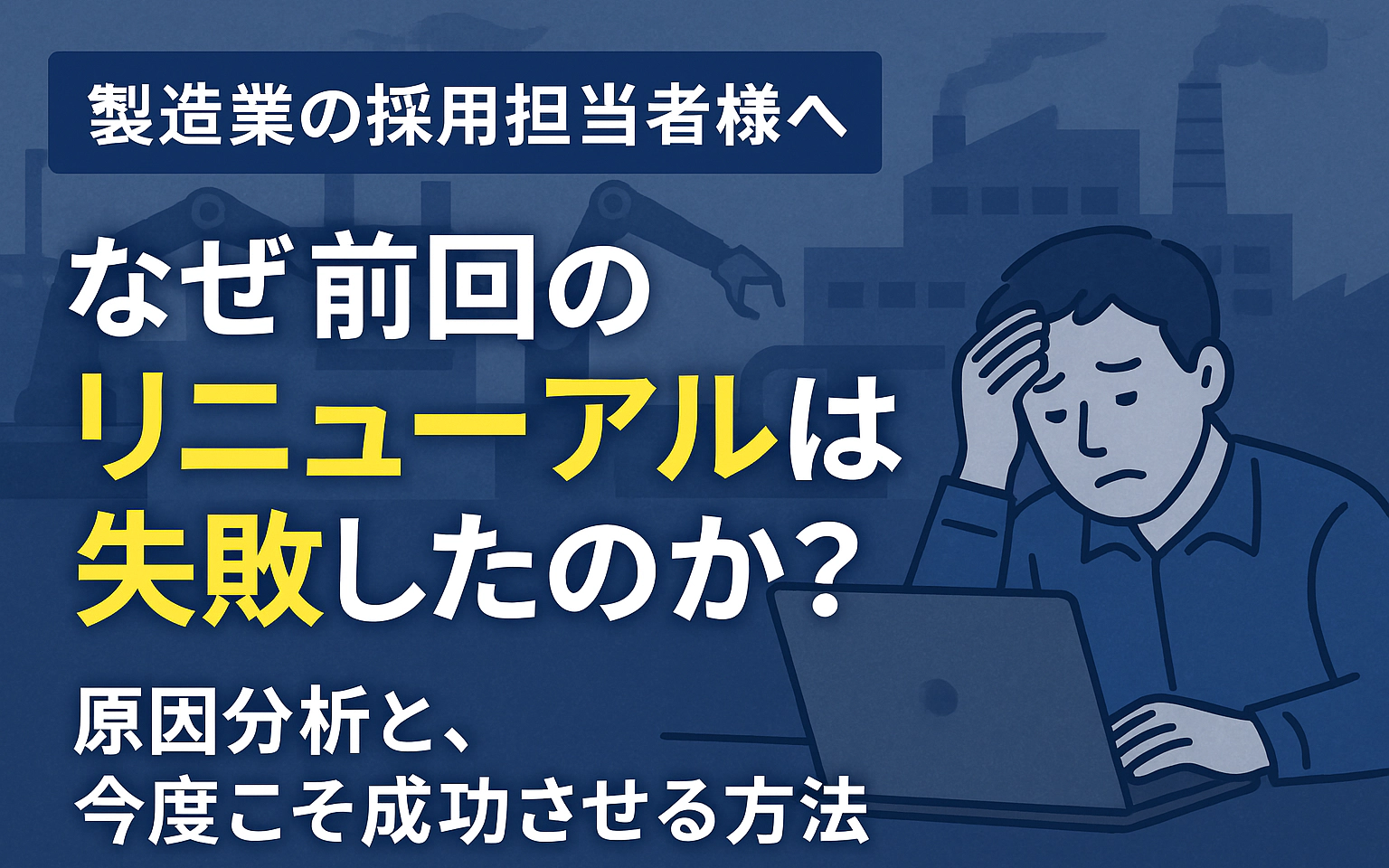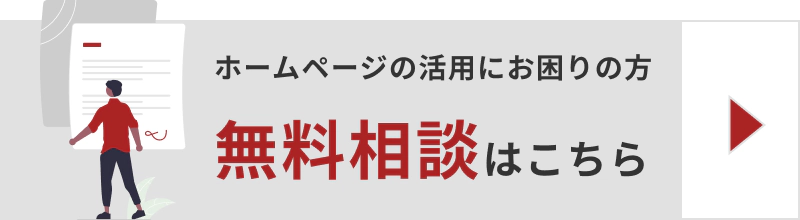「採用活動を強化したい。だけどサイトリニューアルは、気が重い」そう感じていませんか?
「前回の採用サイトリニューアルに200万円近くかけたのに、応募者がほとんど増えなかった。また同じことになるかもしれない…。」そんな不安を抱えたことはありませんか?
私は自動車部品メーカーとセラミックス部品メーカーで生産技術職として働いてきた経験があり、転職活動の際には数多くの製造業のサイトを見てきました。現在は製造業専門のホームページ制作に携わる中で、多くの採用担当者様から同じようなお悩みをお聞きしています。
- 「前回のリニューアルで費用をかけたのに、結果が出なかった」
- 「デザインは確かに良くなったが、応募者数は全く変わらない」
- 「そもそも、うちのような工場に立派なサイトなんて本当に必要なのか?」
こうした声をお聞きする中で、失敗には必ずパターンがあり、適切な手順で進めれば成功できると確信しています。
本記事では、ITが苦手な採用担当者様や経営者様でも実践できる、失敗しないサイトリニューアルの進め方を具体的にお伝えします。今度こそ、本当に応募者が増える採用サイトを作るために、一緒に進めていきましょう。
そもそも、製造業でWebサイトリニューアルは本当に必要なのか?
「サイトリニューアルより、設備投資に回した方が良いのではないか?」そのように感じていらっしゃる方もいるかもしれません。しかし、現在の製造業を取り巻く環境と、求職者の情報収集の変化を考えると、Webサイトへの投資は避けて通れない課題となっています。
設備投資 vs Webサイト投資の現実的な判断基準
製造業において、設備投資が生産性向上に直結するため非常に重要であることは言うまでもありません。しかし、どれだけ最新の設備を導入しても、それを使いこなす「人」がいなければ、企業活動は成り立ちません。
製造業における人材不足の現状
現在、製造業は深刻な人材不足に直面しています。「2025年版 ものづくり白書」でも、製造業における人材確保の難しさが指摘されており、特に若年層の技術者不足は深刻化の一途を辿っています。
図:若年就業者(34歳以下)数の推移

引用:2025年版 ものづくり白書「P22 図3 若年就業者(34歳以下)数の推移」
高齢化の進展に伴い、熟練技術者の引退も重なり、この傾向は今後も続くと予想されています。このような状況下で、いかに優秀な人材を確保するかが、企業の存続を左右する喫緊の課題となっています。
採用コストの比較(求人広告 vs 人材紹介 vs サイトリニューアル)
人材確保のための採用活動には、様々な方法があり、それぞれにコストがかかります。
- 求人広告:短期的な集客には効果的ですが、掲載期間や掲載媒体によっては高額になることが多く、継続的な採用には向かない場合があります。また、多くの企業が利用するため、自社の魅力が埋もれてしまう可能性もあります。
- 人材紹介:採用が決定した場合に年収の30%〜35%程度の高額な費用が発生します。専門性の高い人材の採用には有効ですが、多数の採用には不向きであり、コスト負担も大きくなりがちです。
- Webサイトリニューアル:初期投資はかかりますが、一度構築してしまえば、長期的に自社の魅力を発信し続けることが可能です。求人広告や人材紹介のように、採用ごとに費用が発生するわけではないため、長期的に見れば採用コストを大幅に削減できる可能性があります。
採用活動において、Webサイトは24時間365日稼働する「自社の採用広報担当者」となり得るのです。
投資回収期間の具体的シミュレーション
Webサイトリニューアルにかかる費用は、決して安価なものではありません。しかし、その投資がどれくらいの期間で回収できるのか、具体的なシミュレーションをしてみましょう。
例えば、Webサイトリニューアルに200万円を投資し、年間で2名の採用に成功したと仮定します。
もし、人材紹介で2名を採用していた場合、一人当たりの紹介料が年収の35%(例えば年収400万円の場合140万円)だとすると、2名で280万円のコストがかかります。
この場合、Webサイトへの200万円の投資は、初年度で既に人材紹介を利用するよりも低コストで採用を実現でき、実質的に投資を回収できたと言えます。さらに、Webサイトは来年以降も自社の採用活動に貢献し続けるため、投資回収期間は短縮され、費用対効果は年々高まっていきます。
このように、短期的な費用だけを比較するのではなく、長期的な視点で採用コスト全体を捉えることが重要です。
今の求職者のWeb利用実態
「昔はハローワークや工場見学で人材を確保できたのに、今はなぜWebサイトが必要なんだ?」そう思われる方もいるかもしれません。しかし、今の求職者、特に若い世代は、企業情報を得るためにWebサイトを最も重視しています。
求職者の企業情報収集方法の変化
現代の求職者は、就職活動においてインターネットを積極的に活用しています。企業の採用サイトはもちろん、SNS、口コミサイト、ニュース記事など、多角的に情報を収集し、応募する企業を慎重に選んでいます。
特に製造業のような専門性の高い分野では、企業の事業内容、製品、技術力、働く環境など、詳細な情報を知りたいというニーズが高いです。求人情報だけでは伝えきれない企業の魅力を、Webサイトで深く伝えることが、求職者の応募意欲を高める上で不可欠となっています。
年代別のWebサイト重視度データ
企業のWebサイトは、20代〜30代の若手求職者も含め、すべての年齢層において、企業情報を得る上で多くの方が情報源の一つとして閲覧しています。
これは、求職者が「企業がどんな製品を製造しているか」だけでなく、「Webサイトを通して企業がどのような姿勢で情報公開に取り組んでいるか」も判断材料にしていることを意味します。
町工場でも必要な理由
「うちは従業員が少ない町工場だから、立派なWebサイトは必要ないだろう」と考えていませんか?しかし、むしろ町工場こそWebサイトリニューアルの恩恵を大きく受けられる可能性があります。
大手企業と比較して、町工場は認知度が低い傾向にあります。そのため、Webサイトを通じて自社の専門技術、独自の製品、社風、地域への貢献など、他の媒体では伝えきれない「町工場ならではの魅力」を発信することが、優秀な人材を獲得する上で非常に有効なのです。
特に、工場見学やインターンシップの機会を設けている場合、Webサイトでその情報を分かりやすく提示することで、実際に足を運んでくれる求職者を増やすこともできます。
Webサイトは、規模に関わらず、現代の採用活動において企業の顔となる重要なツールなのです。
なぜ前回のサイトリニューアルは失敗したのか?原因分析
ここでは、多くの製造業の企業が陥りがちなWebサイトリニューアルの失敗原因を、実際の現場で起こり得る状況も交えながら、具体的に分析していきます。これらの失敗原因を理解することで、今度こそ成功に導くためのヒントが見えてくるはずです。
【失敗原因1】途中でコンセプトがぶれた
Webサイトリニューアルのプロジェクトが始動した際、明確な目的とコンセプトを設定したはずなのに、途中で方向性が変わり、最終的に何を目指しているのかが不明確なサイトになってしまうケースは少なくありません。
具体的な失敗事例
「当初は『若手技術者向けの採用サイト』として進めていたが、『製品のブランディングも強化したい』となり、急遽方向転換。その結果、採用情報も製品情報も中途半端になり、結局どちらの目的も達成できなかった。」
これは、よくある失敗事例の一つです。プロジェクトの途中で新たな要望が次々と出てきたり、当初の目的が曖昧になったりすると、一貫性のないWebサイトになる恐れがあります。また、追加費用がかかったり、公開の遅延につながることもあります。
防止策:事前合意の重要性
この失敗を防ぐためには、プロジェクト開始前の「事前合意」が何よりも重要です。
- 目的とゴールの明確化:Webサイトリニューアルで何を達成したいのか(例:採用応募数〇件増加など)、具体的なゴールを設定し、経営層を含めた関係者全員で共有し、合意形成を図ります。
- ターゲット像の具体化:誰に情報を届けたいのか(例:20代の理系学生など)を具体的に設定し、そのターゲットが何を求めているのかを深く掘り下げます。
- コンセプトの言語化:ターゲットに何を伝え、どのような印象を与えたいのか、コンセプトを具体的な言葉で表現し、ブレない軸とします。
- 承認プロセスの確立:途中で安易に意見が変更されないよう、各段階での承認プロセスを明確に定めておきましょう。
これらの事前合意を丁寧に行うことで、プロジェクトの途中で方向性がブレることを防ぎ、一貫性のあるWebサイトを構築することができます。
【失敗原因2】現場の協力が得られず、当たり障りのない内容になった
Webサイトは、企業の「顔」となる存在です。特に製造業の場合、現場の技術や製品、そこで働く人々の魅力こそが、求職者や顧客にとって最も知りたい情報です。そのため、サイトリニューアルプロジェクトにおいて、現場の方の協力が必要不可欠です。
現場の協力が得られないと…
- リアルな魅力の欠如:製品や技術の詳しい説明、現場の雰囲気、社員の生の声など、求職者や顧客が本当に知りたい「生きた情報」が不足します。
- 抽象的な表現:具体的な情報がないため、「最先端技術」「高品質」「働きやすい環境」といった抽象的な表現に終始し、他社との差別化が図れません。
- 情報陳腐化の加速:現場で日々生まれる新しい情報や変化をタイムリーに反映できず、情報の鮮度が失われていきます。
現場を巻き込む具体的方法
現場の協力を得るためには、彼らを単なる「情報提供者」としてではなく、「プロジェクトの重要な一員」として巻き込む姿勢が不可欠です。
- 目的とメリットの共有:Webサイトリニューアルが、会社全体、ひいては現場の社員一人ひとりにとって、どのようなメリットをもたらすのかを具体的に説明します(例:優秀な人材の確保で業務負担が軽減されるなど)。
- 役割と責任の明確化:現場の誰に、何を、いつまでに、どのように協力してほしいのかを具体的に伝えます。無理のない範囲で、簡単なアンケートやヒアリングから始めるなど、協力のハードルを下げましょう。
- 現場の声を聞く機会の設置:座談会形式で、社員のホンネや魅力を引き出す場を設ける。若手社員をプロジェクトメンバーに加えるなど、主体的に関わる機会を作ります。
- 写真や動画の活用:文章作成が苦手な現場には、写真や動画の提供を依頼するなど、負担の少ない形で協力してもらえるよう工夫します。プロのカメラマンを派遣し、現場の「普段の姿」を自然に撮影するのも効果的です。
現場の「生きた情報」は、Webサイトの魅力を最大限に引き出すための宝です。根気強く、彼らとのコミュニケーションを深めていくことが、成功へのカギとなります。
【失敗原因3】制作会社が製造業を理解していなかった
Webサイト制作のプロフェッショナルであるWeb制作会社に依頼したにもかかわらず、最終的に期待外れのサイトになってしまう原因の一つに、「制作会社が製造業の特性や課題を十分に理解していなかった」という点が挙げられます。
一般的なWeb制作会社の限界
多くのWeb制作会社は、幅広い業種のWebサイトを手掛けており、デザインやシステム構築に関する専門知識は豊富ですが、製造業のような専門性の高い分野の深い知識や慣習まで持ち合わせているケースは稀ですし、それはやむを得ない部分でもあります。
彼らはヒアリングや提供情報をもとにサイトを制作しますが、製造業特有の用語、技術、商習慣、そして製造現場のリアルな課題については、表面的な理解に留まってしまうことがあります。
業界知識の重要性
製造業のWebサイトを成功させるためには、制作会社が「製造業の業界知識」を持っていることが非常に重要です。
- 的確なヒアリング:業界知識がある制作会社は、貴社の事業内容や製品、強み、課題について、より深く掘り下げたヒアリングが可能です。
- ターゲットへの訴求力:製造業の求職者や顧客がどのような情報を求めているかを理解しているため、彼らの心に響くコンテンツやデザインを提案できます。
- 専門用語の分かりやすい表現:専門用語を避けつつも、技術的な正確さを損なわない表現方法や、図解での説明など、分かりやすさへの工夫ができます。
Web制作会社を選ぶ際には、実績だけでなく、製造業のWebサイト制作経験や、業界に対する理解度をしっかりと見極めることが大切です。
【失敗原因4】公開後の運用体制を考えていなかった
Webサイトのリニューアルは、新しいサイトが完成し、公開された時点で「成功」と誤解されがちです。しかし、公開はスタート地点に過ぎません。多くの企業が、サイト公開後の運用体制や、具体的な目標達成に向けた活動を十分に考慮していなかったために、結果として「作って終わり」になり、成果が得られないまま失敗に終わってしまいます。
運用体制の不備
Webサイトは公開後も継続的な更新が必要です。しかし、下記のような問題に直面することもあります。
- 「更新方法が複雑で社内で誰も担当できない」
- 「簡単なニュース更新に毎回制作会社への依頼と費用がかかる」
- 「CMS(コンテンツ管理システム)の使い方が難しくて誰も更新できない」
- 「公開後はサポートがなく、困っても相談できない」
このような状況では、Webサイトの更新が滞り、情報が古くなってしまいます。製造業では、新技術開発、製品改良、社員紹介、イベントなど日々新しい情報が生まれます。特に採用サイトでは、情報の鮮度が応募意欲に直結します。古い情報のままでは、求職者に貴社の「今」を伝えられず、人材獲得の機会を逃してしまう可能性があります。
防止策:公開後の目標と運用を見据えた計画
Webサイトを成功させるには、公開前から具体的な目標設定と運用計画を立て、実行する体制を整えることが不可欠です。
- KPIの設定:具体的な数値目標を設定します(例:サイト訪問者数、採用情報ページへの遷移率、応募数など)。これらの数値を定期的に計測・分析し、目標達成に貢献しているか把握します。
- 効果測定ツールの活用:Google Analytics 4 (GA4) などのアクセス解析ツールを導入し、そのデータの見方や分析方法について制作会社と事前に共有します。数値だけでなく、「なぜこの数値なのか」「どう改善するか」を議論し、アクションに繋げましょう。
- 更新担当者の決定と育成:社内でWebサイトの更新担当者を明確に定め、管理方法や簡単なコンテンツ作成スキルを習得させます。制作会社にレクチャーを依頼したり、マニュアルを作成してもらったりして、自社でスムーズに更新できる体制を構築します。
- 制作会社との運用サポートの確認:契約前に、公開後のサポート内容(保守費用、緊急時の対応、追加修正の費用体系など)を具体的に確認し、書面で合意しておきましょう。
Webサイトのリニューアルでは、運用体制の構築にぜひ力を入れてください。
今度こそ成功する!戦略立案の具体的プロセス
ここまでは、失敗原因と各防止策について考えてきました。
ただ、今度こそ成功に導くためには、目的を明確にし、ターゲットに響くメッセージを届けるための戦略立案が不可欠です。
ここからは、製造業の皆様が実践しやすい、具体的で実務的な戦略立案のプロセスをステップごとに解説していきます。
【ステップ1】社内合意形成の実務的手順
Webサイトリニューアルプロジェクトの成功は、社内の協力体制にかかっています。特に、経営層と現場社員の双方から理解と協力を得ることが重要です。
経営層との合意項目チェックリスト
- リニューアルの目的と目標:「なぜリニューアルするのか」「リニューアルによって何を達成したいのか(例:採用応募数20%増、特定技術への問い合わせ5件増など)」を具体的に提示します。
- 投資対効果の見込み:サイトリニューアルにかかる費用に対して、どのようなメリット(例:人材紹介費の削減、営業効率の向上など)が得られるのか、具体的なシミュレーションを提示し、投資としての妥当性を説明します。
- プロジェクトの責任者と体制:プロジェクトの最高責任者(例えば経営者自身や人事部長)を明確にし、推進体制を図示して協力体制を明確にします。
- 予算とスケジュール:具体的な予算枠と大まかなスケジュールを提示し、承認を得ます。
- 意思決定のプロセス:途中で方針がぶれないよう、誰が、どの段階で、どのような最終承認を行うのかを事前に決めておきます。
これらの項目をまとめた資料を作成し、事前に合意を得ることで、経営層の理解と信頼を引き出すことができます。
現場との調整
- 目的の共有とメリットの訴求:「Webサイトリニューアルが、会社全体、ひいては皆さんの働き方にも良い影響を与える(例:優秀な人材が増えれば業務負担が軽減される、会社の知名度が上がれば誇りにつながる)こと」を具体的に伝えます。
- 負担軽減への配慮:現場社員に協力を求める際は、彼らの業務負担を最小限にする工夫が必要です。例えば、文章作成を依頼するのではなく、インタビュー形式で話を聞き出し、担当者が文章にまとめる。写真撮影もプロに任せ、現場は普段通りの作業に集中してもらう、といった配慮が有効です。
- 情報提供の簡易化:現場からの情報提供は、専用のフォームを設けたり、気軽にメモ書きで提出できるような仕組みを作ったりするなど、できるだけハードルを下げましょう。
- 感謝とフィードバック:協力してくれた社員には感謝を伝え、Webサイトの具体的な成果を共有することで、次の協力にも繋がりやすくなります。
プロジェクトチーム編成
- 多様なメンバー構成:部門横断チームがベストです。例えば、経営層、人事・採用担当者、現場のベテラン社員、若手社員、広報担当者など、多角的な視点を持つメンバーを選定します。特に若手社員や現場のキーパーソンは、求職者目線での意見や、リアルな現場の情報提供に貢献してくれるでしょう。
- 明確な役割分担:各メンバーの役割と責任を明確にし、誰が何を決定し、誰に報告するのかをプロジェクト開始前に共有します。
- 定例会議の実施:進捗状況の確認や課題の共有、意見交換を行うことで、認識のズレを防ぎます。
【ステップ2】ターゲット人材の明確化
「今の若い技術者や求職者は、一体どんなホームページなら応募しようと思うんだ?」という疑問に答えるためには、まず「どんな人材に来てほしいのか」を明確にすることが重要です。可能なら、具体的なターゲット像を深掘りするワークショップを実施しましょう。
具体的な議論項目と進行方法
- 現状の人材課題の共有:
- 現在、どのような人材が不足しているのか?(例:特定の技術を持つ経験者、若手の機械設計士など)
- 採用活動において、どのような課題を感じているか?(例:応募数が少ない、ミスマッチが多いなど)
- 理想の人材像の洗い出し:
- 貴社で活躍している社員はどんな人か?(性格、スキル、価値観など)
- 新しく入社してほしい人材はどんなタイプか?
- ターゲットの行動とニーズの考察:
- そのターゲットは普段、どんな情報収集をしているか?(Webサイト、SNS、口コミ、求人情報誌など)
- 貴社に何を求めているか?(給与、福利厚生、仕事内容、職場の雰囲気、技術力、成長機会など)
- 貴社のWebサイトでどんな情報が見たいか?
社内アンケートの設計と実施
より多角的な視点を取り入れるために、社内アンケートも有効です。
- 対象者:現場社員(特に若手、中堅、ベテランの各層から)
- 質問項目例:
- 「貴社で働く中で最も魅力的だと感じる点は何ですか?」
- 「入社前に知っておきたかった情報はありますか?」
- 「もし友人に当社を勧めるなら、どの点をアピールしますか?」
- 「どのようなタイプの人が貴社で活躍できると思いますか?」
- 「当社のWebサイトで改善してほしい点はありますか?」
- 実施方法:匿名回答にすることで、社員の本音を引き出しやすくなります。
ペルソナ設定の製造業版
上記で得られた情報を基に、具体的な「ペルソナ」を設定します。ペルソナとは、ターゲットとなる理想の人材を、まるで実在する一人の人間のように詳細に設定した仮想の人物像です。
製造業向けペルソナ設定の例:
- 氏名:山田 健太(仮名)
- 年齢:26歳
- 現在の職業:大手部品メーカーの製造ラインオペレーター
- 学歴:高卒、専門学校で機械加工を専攻
- 家族構成:独身、実家暮らし
- 性格:手先が器用で、黙々と作業に没頭するのが好き。最新技術への関心も高く、スキルアップ意欲が強い。
- 情報収集方法:技術系ブログやYouTubeで情報収集。求人サイトも見るが、企業のWebサイトで詳細な技術情報や社員のインタビュー記事を重視する。
- 転職理由:現在の会社では、決められた作業が多く、自分のアイデアや技術を活かす機会が少ないと感じている。もっと専門性の高い仕事に挑戦し、技術者として成長したい。
- 貴社に求めるもの:
- 特定の加工技術を極められる環境
- 新しい設備や技術への投資
- ベテラン社員から直接指導を受けられるOJT制度
- 社員が技術について語るブログや動画コンテンツ
- 具体的な製品開発事例
- (できれば)社員食堂や福利厚生の情報
このように、具体的な人物像を描くことで、そのペルソナに響くWebサイトの構成やコンテンツ内容を具体的に検討できるようになります。
【ステップ3】自社の魅力の棚卸しと差別化ポイント抽出
ターゲット人材が明確になったら、次に貴社がそのターゲットに対して何をアピールできるのか、自社の魅力を深く掘り下げ、競合他社との差別化ポイントを見つけ出します。
現場社員へのヒアリング方法
Webサイトで発信する「生きた情報」は、現場に眠っています。現場社員へのヒアリングは、その宝を発掘する重要な手段です。
- 個別インタビュー形式:一人ひとりの社員に時間を設け、じっくり話を聞くことで、普段見えない魅力や本音を引き出せます。
- 質問項目例:
- 「貴社で働く中で、やりがいを感じる瞬間はどんな時ですか?」
- 「入社して驚いたこと、想像と違ったことはありますか?」
- 「職場の雰囲気や人間関係について教えてください。」
- 「貴社の製品や技術で、特に誇れる点はどこですか?」
- 「仕事で困難に直面した時、どのように乗り越えましたか?」
- 「将来、貴社でどんなことに挑戦したいですか?」
- 共感と傾聴:相手の話をさえぎらず、共感しながら聞くことで、社員は安心して本音を話してくれます。
競合分析の具体的手順
貴社の魅力を際立たせるには、競合他社がどのようなWebサイトを運営し、どのような情報を発信しているかを分析することが有効です。
- 競合企業の選定:貴社と同じ地域で、同じような事業内容の企業や、ターゲットとする人材が応募しそうな企業を5〜10社程度選びます。
- Webサイトの比較分析:
- デザイン・使いやすさ:見やすいか、情報が探しやすいか、スマートフォン対応はどうか。
- コンテンツ内容:採用情報、技術情報、製品情報、企業文化に関するコンテンツが充実しているか。
- 写真・動画の質:現場の雰囲気や製品の魅力が伝わるか。
- 求職者への訴求ポイント:どんなメッセージを強く打ち出しているか。
- 更新頻度:ニュースやブログが定期的に更新されているか。
- 貴社の立ち位置の把握:競合他社のWebサイトと比較して、貴社のWebサイトが「優れている点」「劣っている点」「独自性がある点」を明確にします。
強みの言語化テクニック
ヒアリングや競合分析で得られた情報を基に、貴社の「強み」をターゲットに響く言葉で言語化します。
- 具体的なエピソードを添える:単に「技術力がある」ではなく、「〇〇の技術で、□□という課題を解決し、お客様から感謝された」のように、具体的なエピソードや事例を交えることで説得力が増します。
- 数字で裏付ける:「高品質」だけでなく、「不良品発生率0.01%以下を維持」のように、可能な限り数字で裏付けます。
- 求職者メリットに変換する:「弊社の強みは〇〇です」と自慢するだけでなく、「この〇〇という強みがあるからこそ、貴方は弊社でこんな成長機会を得られます」と、ターゲットにとってのメリットに変換して伝えます。
【ステップ4】若い求職者に響くコンテンツ設計
明確になったターゲットと貴社の魅力を結びつけ、具体的なWebサイトのコンテンツに落とし込みます。特に若い求職者は、企業の「リアル」な情報を求めています。
製造業求職者が本当に知りたい5つの情報
若い求職者が製造業のWebサイトで特に知りたい情報は以下の5点です。
- 具体的な仕事内容とやりがい:一日の流れ、担当業務、どのような製品に携われるのか、その仕事の面白さや難しさ、達成感を具体的に伝えます。
- 職場の雰囲気と人間関係:実際に働いている社員の声、部署の紹介、休憩時間の過ごし方など、社員同士の繋がりがわかるコンテンツは、入社後のミスマッチを防ぎます。
- 技術力と成長機会:貴社がどんな技術を持っているのか、新しい技術への取り組み、社員のスキルアップ支援(資格取得支援、研修制度など)を具体的に示します。ベテランから若手への技術継承の様子なども魅力的です。
- キャリアパスと将来性:入社後のキャリアアップの例、部署異動の可能性、会社の今後の展望などを提示し、長期的に働けるイメージを持ってもらいます。
- 会社の安定性と福利厚生:経営基盤の安定性、給与体系、休日休暇、福利厚生(社員食堂、住宅手当など)は、生活の基盤となるため重要な情報です。
これらの情報を、分かりやすく、かつ正直に伝えることが重要です。
町工場の魅力の伝え方
「うちみたいな町工場の魅力って、どうすれば伝わるんだ?」という悩みは多いでしょう。町工場には大手企業にはない独自の魅力があります。
- 専門技術の深掘り:大手では難しい、ニッチだが高い専門性を持つ技術や、熟練の職人技を、写真や動画を多用して紹介します。
- 「顔が見える」職場環境:少人数ならではの雰囲気、経営者やベテラン社員との距離の近さを強調し、親身な指導やサポート体制をアピールします。
- 製品へのこだわりと情熱:大量生産ではない、一つひとつの製品にかける想いや、お客様との関係性をストーリーとして伝えます。
- 地域貢献の側面:地域に根ざした活動や、地域産業への貢献など、地元密着型企業ならではの魅力を発信します。
- 多能工の育成:一つの工程だけでなく、多様な業務を経験できる、幅広いスキルを身につけられるといった町工場ならではの成長機会をアピールします。
現場の声を活かしたコンテンツ作り
現場社員のリアルな声は、Webサイトの信頼性と魅力を高めます。
- 社員インタビュー:若手からベテランまで、様々な立場の社員にインタビューし、仕事のやりがい、会社の雰囲気、今後の目標などを語ってもらいます。顔写真や簡単なプロフィールを添えると、より親近感が湧きます。
- 現場の一日:特定の職種や社員の一日を、写真や動画で追いかけるコンテンツは、仕事内容を具体的にイメージするのに役立ちます。
- Q&A:求職者からよくある質問を、社員が答える形式で掲載します。率直な回答は、企業の誠実さをアピールできます。
- 技術ブログ・動画:現場の技術者が、日々の業務で培った技術や、製品へのこだわりをブログ記事や短い動画で発信します。専門性の高さと、社員の主体性をアピールできます。
これらのコンテンツは、単に情報を羅列するのではなく、ペルソナが「自分ごと」として捉えられるような、ストーリー性や共感性を意識して作成することが重要です。
採用サイトリニューアルでお悩みの担当者様へ
これまでの記事で、前回のWebサイトリニューアルがなぜ期待通りの成果に繋がらなかったのか、そして今度こそ成功させるための具体的な戦略立案のプロセスについて解説してきました。製造業におけるWebサイトは、もはや単なる情報発信の場ではなく、人材獲得競争を勝ち抜き、企業の未来を築くための重要な投資です。
今回の内容を通じて、「誰に、何を、どう伝えるか」という戦略の重要性、そしてそれを実現するための実務的な進め方をご理解いただけたのではないでしょうか。
最後に、今日からすぐにでも始められる具体的なアクションと、成功確率を高めるための重要なチェックポイントをお伝えします。
今すぐ始められる3つのアクション
- 社内合意形成のためのキックオフミーティング開催:Webサイトリニューアルの目的と目標を共有しましょう。
- 現状サイトの問題点洗い出し:客観的に問題点を洗い出してみましょう。可能であれば、若手社員や最近入社した社員に意見を聞いてみるのも有効です。
- 制作会社選定のための情報収集開始:複数のWeb制作会社の情報を集め始めましょう。問い合わせる前に、自社の課題と目的を整理しておくことが、スムーズなコミュニケーションに繋がります。
成功確率を高める5つのチェックポイント
- プロジェクト開始前の合意形成
- 現場を巻き込んだコンテンツ作り
- 製造業に理解のある制作会社選定
- 運用を見据えた管理体制の構築
- 継続的な改善サイクルの構築
Webサイトリニューアルは、単なるITプロジェクトではなく、貴社の採用戦略、ひいては経営戦略そのものです。これらのポイントを意識し、貴社にとって最適なWebサイトを構築することで、今度こそ採用活動強化の成功を掴み取れることを願っております。
私たちは、製造業に特化したWeb制作会社です。
私たちは、Webサイト制作の専門家として、お客様一人ひとりの課題に深く向き合い、最適な解決策を提供することを使命としています。
製造業特有の商習慣、専門技術、そして現場のリアルな声の重要性も、私たちは真摯に学び、理解を深める努力を惜しみません。「技術者の専門用語が理解できない」「工場での写真撮影が難しい」「若手社員がどんな情報を求めているか分からない」といったお悩みも、貴社と共に解決策を考え、最善のWebサイトを創り上げていきます。
私たちは、単にWebサイトを「作る」だけでなく、貴社ならではの戦略立案から、効果測定、そして公開後の運用まで、一貫してサポートいたします。Webサイトを通して貴社の問題解決を実現できるよう、全力で伴走させていただきますので、お気軽に無料相談からお問い合わせください。